子どものコレクション欲をかき立てる存在、どんぐり。

子どもが初めてどんぐりを拾った日。
小さな手で一生懸命、小さなどんぐりを拾っては「アッタ!」
なんてかわいいの‥。
それから早数年。
秋になるたびにどんぐりを拾い続ける子ども。
もう1000個は拾ってる。
「うちの子ったらかわいいわ」ではなく「もういい。もういらない。」になってしまった私。
「たくさん拾ったね」で済ませてあとでこっそり捨てる私。
これではいけない!
うちのママには見せ甲斐がないんだよなあ。なんて思われたくない(悔しい)!
子どもがどんぐりを拾うのはあと数年だけ(の、はず)。
それまではどんぐりトークできるママでいるんだ!と決意しました。

さっそく今年のどんぐりコレクションを広げてみると‥(上の写真はごくごく一部です)。
どんぐりの種類が何種類もあることがわかります。
あたりまえだけど、「どんぐり」という名前の植物はないんですよね。
これ、なんていう木のどんぐりなんだろう。
どんぐりの種類の調べ方
そもそもどんぐりとは、ブナ科の植物の果実の総称。
日本には22種類もあるそうです!
日本自然保護協会のホームページを見ると、どんぐりは、まず帽子の形で分類し、それから帽子の特徴を観察して、木の種類を調べる方法が紹介されていました。
ちなみに、日本自然保護協会では、帽子のことを「パンツ」と呼んでいました。
「パンツ」呼び、子どもウケは抜群に良さそうですね!
なので、この記事でもパンツと呼びたいと思います。
STEP1. パンツの形の観察
パンツの形状は大きく分けて4種類。
- トゲトゲパンツ(パンツがもじゃもじゃしている)
- チューリップパンツ(実がパンツにすっぽり包まれている)
- ウロコパンツ(ウロコ模様のパンツ)
- シマシマパンツ(しましま模様のパンツ)
文章で書くと頭がおかしくなりそう!笑
STEP2. パンツと、パンツじゃない部分の観察
STEP1.で大きく4種類に分けた後は、パンツの深さやパンツじゃない部分の模様、毛が生えているか、お尻の部分はへこんでいるか‥など多種多様な見極めポイントで分類していきます。
覚えきれない。奥が深すぎる。。
ちょっと書ききれないので、詳しく知りたい方は、日本自然保護協会のホームページをご覧くださいね。
子どものどんぐりコレクションの分類結果
早速、結果発表です!
日本自然保護協会のやり方に沿って分類すると、わが家の集めたどんぐりは全部で4種類あることがわかりました!

へぇ~~~~!!
緑で黒い縞模様がついたどんぐり、うちではずっと「スイカどんぐり」と呼んでいましたがアラカシという種類の木なんですね。
クヌギのことは「もじゃもじゃどんぐり」。
コナラは「ふつうの」。シラカシは「小さいの」。
名前がわかると、頭がよくなった気がします!
今日さっそく、ドヤ顔で教えてみよう。
ただ、上の画像の左下、たぶんシラカシなんですが、いまいちわからなかったです。
葉の裏が白ければシラカシなんですが、どこで採ってきたかわからないのでなんともいえません。
これから小さいのを拾うときは葉っぱを観察してきてね、と伝えようと思います。
恐怖のどんぐり穴

上の画像のどんぐりをみて、恐怖を覚えるママは多いでしょう。
穴の開いたどんぐりや、割れているどんぐりの中には、高い確率で幼虫がいます。
拾ってきたどんぐりを部屋のどこかにポイっと置きっぱなしにしたり、ポケットの中に入れっぱなしにしておくと、気づいた時には幼虫がウヨウヨ‥なんてことになりかねません。
ヒェッ~~~~~!
春はダンゴムシ、秋はどんぐり‥
子どものポケットチェックは春秋は欠かせませんね。
まとめ

ひとくちに「どんぐり」といってもその種類はたくさん。
種類の見極めは、パンツ(帽子)の形状の観察が重要だとわかりました。
これから、初めて見るどんぐりは、ちゃんとパンツ履いているのを拾ってくるようにね!と伝えたいと思います。
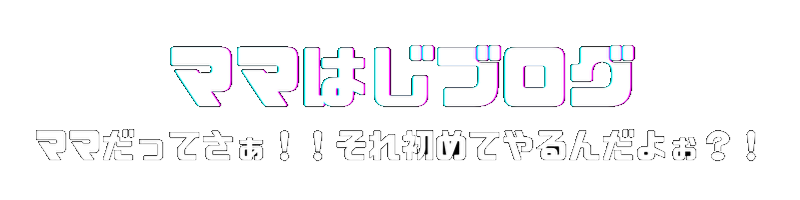


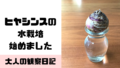
コメント