子どもがもし、カタツムリを捕まえてきたら‥

梅雨時になると現れるカタツムリ。
その見た目やカタツムリの歌から、子どもには人気の生き物です。
ゆっくり動くし殻があるから捕まえやすく、子どもが家に連れて帰ってきやすい生き物でもあります。
でも、ヌメヌメじとじとしていて、大人では苦手な人も多いですよね。
「これ飼いたい!」とキラキラした目で言われたとき、「きもちわるっ!」と言ってしまいそうになるのをぐっとこらえて、よく見てみてください。
なんだかかわいく見えてくる‥かもしれない生き物です。
このカタツムリ、ご安心ください!
飼うのは超イージーです。
手間もお金もかからず、簡単に飼うことができます。

生息場所
湿気が好きな生き物です。
じめっとした日には植物の葉の陰などで元気に活動しています。
カラッと晴れた暑い日には、日陰に身を隠してじっとしています。
特徴
雌雄同体
オスとメスの区別がありません。
雌雄同体といって、体にオスとメスそれぞれの生殖器官を持っています。
よく寝る生き物
カタツムリは種類や大きさによりますが、1年以上生きる(長いものでは10年以上!)ことができるといわれています。
でも、一年中元気に活動しているわけではありません。
自分で体温を調節できない生き物なので、寒すぎると冬眠をして、暑すぎると夏眠をします。
夏眠ってあまり聞かないワードですよね。
冬眠は、15度より寒くなる10月頃~3月に。
夏眠は、カラッと晴れてめちゃくちゃ暑い7月~8月に。
つまり、春~梅雨時と秋のわずかな期間しか、元気に動いているのを見られない生き物なんですね。
冬眠・夏眠どちらも、石や朽ち木や落ち葉の裏側など、乾燥しない場所でひっそり眠ります。
室温が一定の暖かい部屋で飼うなら、冬眠も夏眠もせずに活動し続けます。
食べるもの
野菜や果物と、卵の殻が必要です。
エサ代がかからないので助かりますね。
飼育ケースの中は湿度が高いのですぐにかびてしまうので、毎日交換してあげましょう。
また、ケースの床に直置きだと汚くなるので、お醤油皿など小さいお皿か、お弁当のおかずカップなどに入れるといいですよ。
野菜や果物
捨ててしまうような切れ端でOKです。
どんな野菜でも食べます。
卵の殻
背負っている殻をつくるため、カルシウムが必要です。
カタツムリの歯は強いので、卵の殻を砕いて食べることができます。
食べさせないで!NGエサ
紫陽花とカタツムリ。
よくイラストなどで見る組み合わせなので、つい飼育ケースに紫陽花を入れたくなります。
でも、実は自然界では紫陽花にカタツムリは寄り付きません。
なぜなら、紫陽花の葉には毒があるからです。
カタツムリも紫陽花の葉には毒があるとわかるので食べないとは思いますが、飼育ケースに紫陽花の葉は入れないようにしましょう。
飼い方
ケース・小枝や石・霧吹きがあればOK!
直射日光の当たらない風通しの良い日陰で飼いましょう。
ケース
プラスチック製・ガラス製どちらでもOKです。
壁を登って逃げるので、蓋のついたものを用意しましょう。
密閉状態にならないように、網目の蓋のものがいいです。
穴をあけたラップでも代用可能です。
ケースの底には、乾燥防止のため、土または濡らした紙を敷きます。
こまめに霧吹きで湿度を与えていれば、何も敷かなくても飼うことはできますが、這いずり回ったべとべとの跡や糞の掃除が面倒なので、何か敷いた方が絶対にいいです。
小枝や石
カタツムリが登ったり下りたり動けるように、また、体を隠せるように小枝や石を置きます。
霧吹き
湿った環境が好きなので、1日1~2回、霧吹きでケース内を十分に湿らせます。
飼うときの注意
カタツムリには寄生虫がいます。
人体に有害な寄生虫もいるので、カタツムリを触ったら手をよく洗うように徹底しましょう。
飼育ケースを洗うときは、キッチンで洗わないことや、うがい用のコップや歯磨きなど口に入るもののそばで洗わないことに注意しましょう。
子どもが喜ぶカタツムリ実験
糞の観察
カタツムリは食べたものと同じ色の糞をします。
ニンジンをあげてみたり、小松菜をあげてみたりして糞の観察をすると盛り上がります。
まとめ
- カタツムリ飼育のハードルは低い
- 日々のお世話はエサの交換と霧吹き
- 小さい子供でもお世話できる気軽なペット
- よく見るとかわいく思えてくる不思議な存在
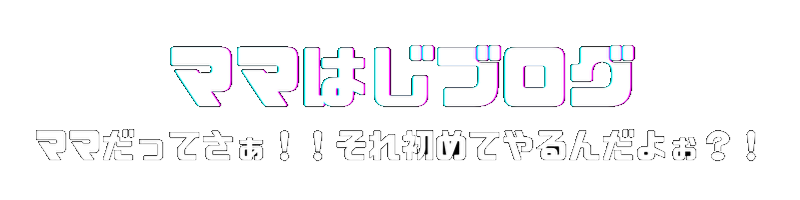
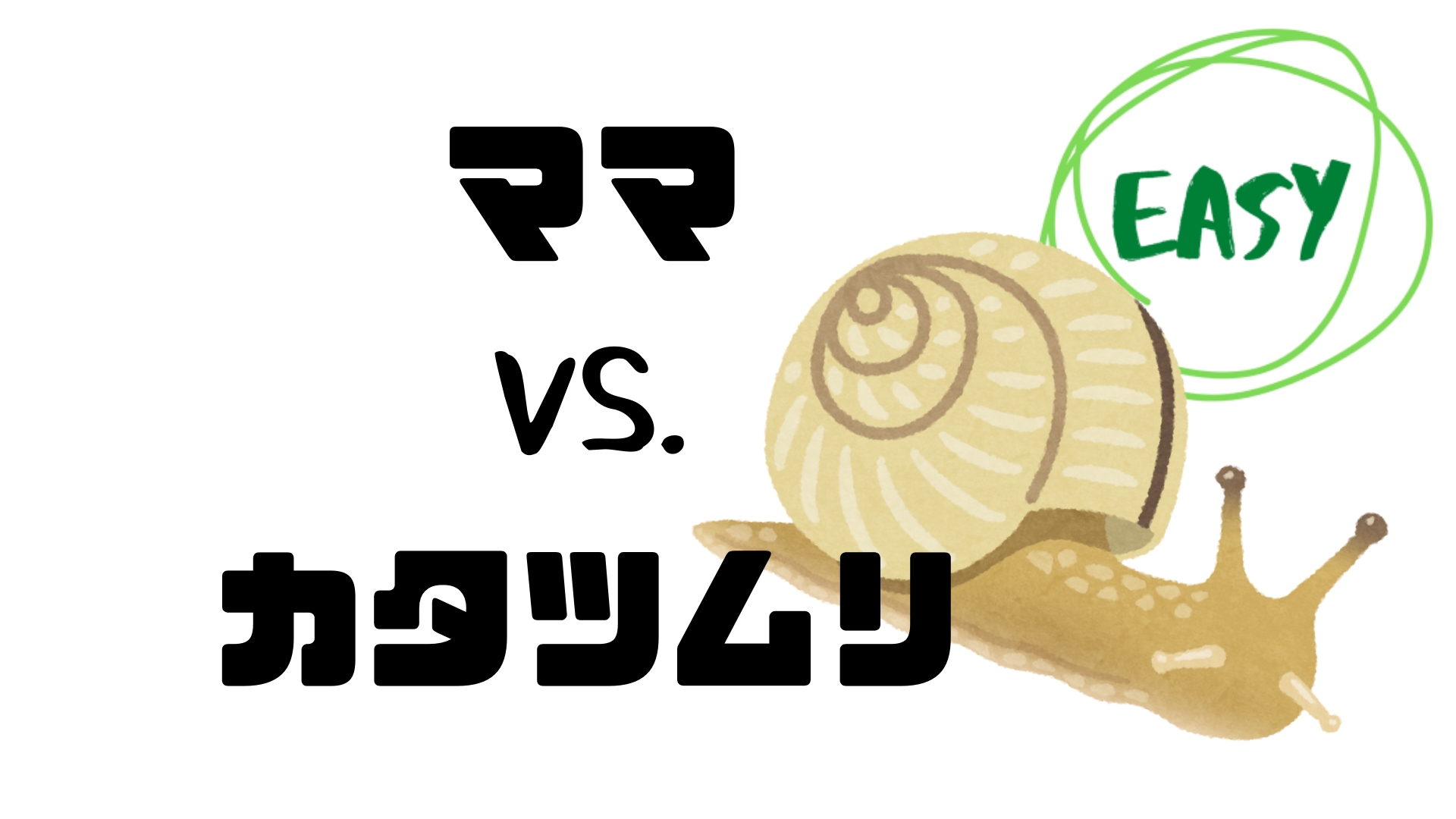


コメント